札幌市の「市民によるヒグマ対策」に学ぶ(市長日記R6.3.13)
令和6年3月13日
この標題は丹波篠山市のものではありません。昨年の秋はよくクマが出てきて問題になりましたが、先日の丹波篠山市の獣がいフォーラムでは札幌市から酪農学園大学教授の佐藤喜和先生にお越しいただき、「市民によるヒグマ対策」としてご講演いただきました。
テーマは「すみ分けによる共存を目指して私たちにできること」というものです。
「札幌市の未来像は『持続可能なグリーンシティさっぽろ』とし、森や自然、緑を大切にした都市計画をつくっています。ところが市街地のすぐ隣が山となっているため、すぐ裏山生まれのクマたちは車や人の気配に慣れ、市街地に侵入するようになりました。そこで共存するためにクマの暮らす『森林ゾーン』、クマが入ってきてはいけない『市街地ゾーン』、クマが入ってくるのを防ぐ『市街地周辺ゾーン』、クマがすみ着くのを防ぐ『都市近郊林ゾーン』ごとに対策を進めています。
市民団体もクマの侵入を防ぐため、草刈りによる景観の改善に取り組んでいます。」
というものでした。
兵庫県でもかなり先進的な取組みをされています。
兵庫県では一時、クマは人里に出てくると有害鳥獣として駆除され、残り60頭、絶滅が時間の問題となりました。そこで、1993年に16人の生徒たちが兵庫県の貝原俊民知事に手紙を書き、知事が出会われました。
生徒たちは貝原知事にたずねました。
「絶滅寸前の兵庫県野生ツキノワグマについて、
1案 野生で絶対に残さなければならない
2案 できたら残した方がいい
3案 どちらとも言えない
4案 できたら駆除したい
5案 すべて駆除したい
あなたはどれをお選びですか」と
知事は即座に、「1案に決まっているよ。野生で残さないと意味ないだろう」と答えられました。
これに続いて、1994年兵庫県での全国植樹祭の時、スギを植える植樹祭から26種類の広葉樹を植えることに変更されました。さらに、当時の環境庁長官が「兵庫県のツキノワグマ、絶滅のおそれにつき狩猟禁止令を発令します」と発表されました。
その後、20年以上にわたって狩猟が禁止されていましたが、生息数が増えたことから2016年に狩猟禁止が解除となり、一定数を捕獲したため2019年には再び狩猟が禁止されています。
札幌市と同じようにゾーンを分けて考えたり、捕獲してもすぐに殺処分せず、花火などの音で威嚇して学習させてから山に返したりなどの配慮もされています。
丹波篠山市もサルなどとの共生を目指しつつ被害対策をとっています。シカやイノシシなども「個体数管理」といって、長い目でみて共生です。クマに比べると理解もされやすいと思います。

佐藤先生 講演

基調講演のスライド(佐藤先生よりご提供)

基調講演のスライド(佐藤先生よりご提供)

基調講演のスライド(佐藤先生よりご提供)

パネルディスカッション 篠山東雲高校

パネルディスカッション さともん 鈴木さん

佐藤先生は丹波篠山市にふるさと納税をされており、返礼品は篠山東雲高校の柿ジャムです。
(画像:佐藤先生よりご提供)





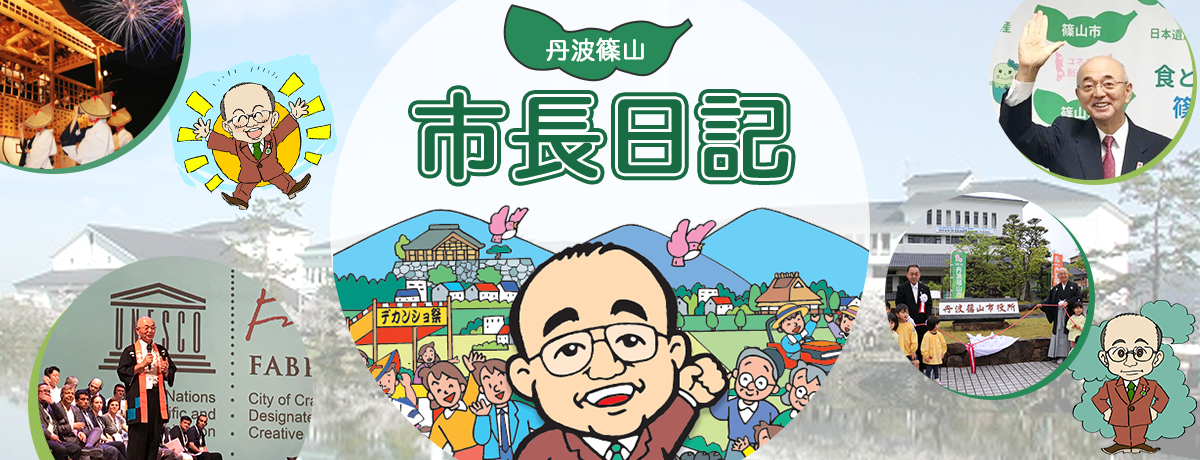

更新日:2024年03月13日