生き物の安易な放流はやめてください
生き物の放流は、ニュースに取り上げられることもあり、よい取り組みのようにも思えますが、環境を守る上では、ほぼ無意味だったり、逆に悪い影響を与えたりすることも少なくありません。
すべての放流がダメというわけではありませんが、まずは「何のためにやるのか」「そもそもなぜ減ってしまったのか」を考える必要があります。
放流する際は、専門家に問題がないかを確認するなど、十分に注意しましょう。
放流がダメな理由
放流しても環境が悪くて生きていけない
暮らしやすい環境が整っていなければ、放流しても生き残るのは難しく、短期間のうちに死んでしまいます(死滅放流)。
病気を移したり他の生き物を食べたりする
放流した生き物が、病気や寄生虫を持ち込んでしまうおそれがあります。
また、天敵がいるところに放せば、食べられてしまい、天敵がますます増えて、他の生き物に悪影響が及ぶおそれもあります。
逆に、放流した生き物が他の生き物を大量に食べ、自然界のバランスを崩してしまうリスクもあります。
地域の遺伝的特徴を失わせてしまう
同じ種でも別の地域にすんでいる生き物同士は遺伝子の特徴が少しずつ違うことがあります。
安易に放流すると、地域独自の遺伝的特徴が失われます。
こんな生き物を放していませんか?
メダカ
丹波篠山市に生息している野生メダカは、同じ加古川や武庫川の下流に生息している野生メダカ、ペット用に市販されている改良メダカとは異なる遺伝的特徴を持っています。
他地域から持ち込んだメダカやペットとして市販されている改良メダカを放流すると、地域固有の遺伝的特徴が失われるおそれがあります。
コイ
川の美化活動として放流が行われることがありますが、生態系に大きなダメージを与えることが分かってきました。
コイは雑食で、水辺にすむ昆虫や貝を食べつくしてしまいます。また、泥と一緒に吸い込むようにして食べるため、水が濁り、水草が光合成できずに死んでしまうという問題も指摘されています。
いま日本にいるコイのほとんどが外来種で、「兵庫県の生物多様性に悪影響を及ぼす外来生物リスト(ブラックリスト)(2010)」や「世界の侵略的外来種ワースト100」にも掲載されています。
コイヘルペスウイルス病のまん延防止に関する指示
兵庫県では、コイヘルペスウイルス病(KHV)まん延防止のため、下記の制限が設けられています(兵庫県公報第269号・兵内漁委指示第80号)。
- 県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面においては、採捕したコイを持ち出して他の水域に放流することは禁止されています。
- 県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面においては、コイを放流する場合は、過去にKHVが発生した水域の水に浸かったことがないものに限り、PCR検査により陰性の確認が必要です。
- 生死を問わず、コイを河川等に遺棄してはいけません。
外来種
ブルーギルやブラックバス、ウシガエルなどは、外来生物法による特定外来生物に指定されており、野外に放つことが禁止されています。
ザリガニ、アカミミガメ(ミドリガメ)、グッピー、外国産カブトムシなどは、環境省の「生態系被害防止外来種リスト」に掲載されています。飼育への規制はありませんが、野外に逸出しないよう注意が必要です。
その他
ホタル、カワニナ、サギソウなど、在来種であっても、他の地域から持ち込むことで、もとからその地域にいる生き物に影響を与える場合がありますので、放流しないでください(国内外来種)。
また、金魚などの人工改良品種も、もとからその地域にいる生き物に影響を与えるため、放流はやめてください。
放流に関するガイドライン
絶滅を避ける最後の手段としての放流・再導入が成功した例もあります。
学会や研究機関が、生物多様性保全の視点から見た注意点をまとめて公開していますので、ご参照ください。
「生物多様性の保全をめざした魚類の放流ガイドライン」日本魚類学会
この記事に関するお問い合わせ先
農村環境課 創造農村室
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)
電話番号:079-552-5013
メールフォームによるお問い合わせ









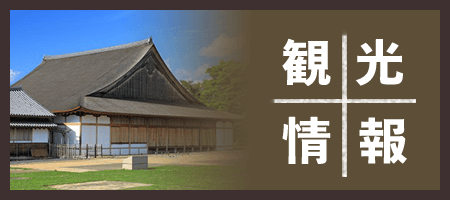
更新日:2023年05月17日