市県民税(所得の種類、諸控除額)
10種類の所得と所得金額の計算方法
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 利子所得 | 公社債や預貯金の利子、合同運用信託や公社債投資信託の収益の分配などによる所得 | 【収入金額=利子所得】 一般的に、利子所得は源泉分離課税のため申告は不要です。ただし、国外で支払われる預金利子など、国内で源泉徴収されないものなどは申告が必要です。 |
| 2 | 配当所得 | 法人から受ける剰余金の配当、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等の運用投資信託を除く)の収益の分配などの所得 | 【収入金額-株式などの元本を取得するために要した負債の利子(赤字のときは0円)】 |
| 3 | 不動産所得 | 土地・建物などの不動産や不動産上の権利などの貸し付けにより生ずる所得(地代・家賃・権利金など) | 【総収入金額-必要経費-専従者控除額(注釈:下記参照)】
|
| 4 | 事業所得 (営業等・農業) |
個人商店の経営、医師・弁護士などの自由業、または農業などから生ずる所得 | 【総収入金額-必要経費-専従者控除額(注釈:下記参照)】
|
| 5 | 給与所得 | 俸給・給料・賃金・賞与などの給与および専従者給与にかかる所得 | 【収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額】 給料の額(年収)に応じて計算方法が決まっています。 |
| 6 | 退職所得 | 退職金や一時恩給などによる所得 | 【(収入金額-退職所得控除額)×1/2】 |
| 7 | 山林所得 | 山林(保有期間が5年を超えるもの)を伐採して売却したり、立木のまま譲渡することにより生ずる所得 | 【総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)】 |
| 8 | 譲渡所得 | 土地・建物、借地権などの土地の上に存する権利や株式など資産の譲渡により生ずる所得 | 【総収入金額-(資産の取得費+譲渡費用)-特別控除額】 |
| 9 | 一時所得 | 懸賞の賞金品、競馬等の払戻金、生命保険や損害保険の満期保険金や返戻金などの一時的に得る所得 | 【総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)】 |
| 10 | 雑所得 | 公的年金等の収入や、業務(副業に係る収入のうち、営利を目的とした継続的なもの)個人年金保険の年金、原稿料・講演料など上記のいずれの所得にも当てはまらない所得 | 次の1と2の合計額
|
給与所得額の計算方法
給与収入額が162万8千円未満の方の場合
| 給与収入額 | 給与所得の金額 |
|---|---|
| 55万1千円未満 | 0円 |
| 55万1千円以上161万9千円未満 | 収入額-55万円 |
| 161万9千円以上162万円未満 | 106万9千円 |
| 162万円以上162万2千円未満 | 107万円 |
| 162万2千円以上162万4千円未満 | 107万2千円 |
| 162万4千円以上162万8千円未満 | 107万4千円 |
給与収入額が162万8千円以上660万円未満の方の場合
まず給与収入額を4で割って、千円未満の端数を切り捨てます。
| 4で割った給与収入額 | 給与所得の金額 |
|---|---|
| 40万7千円以上44万9千円以下 | 4で割った収入額×2.4+10万円 |
| 45万円以上89万9千円以下 | 4で割った収入額×2.8-8万円 |
| 90万円以上164万9千円以下 | 4で割った収入額×3.2-44万円 |
給与収入額が660万円以上の方の場合
| 給与収入額 | 給与所得の金額 |
|---|---|
| 660万円以上850万円未満 | 収入額×0.9-110万円 |
| 850万円以上 | 収入額-195万円 |
公的年金所得額の速算表
| 年金受給者 | 公的年金の収入額 | 所得計算式 |
|---|---|---|
| 65歳未満の方 | ~130万円未満 | 収入額-60万円 |
| 130万円以上~410万円未満 | 収入額×0.75-27万5千円 | |
| 410万円以上~770万円未満 | 収入額×0.85-68万5千円 | |
| 770万円以上~1千万円未満 | 収入額×0.95-145万5千円 | |
| 1千万円以上 | 収入額-195万5千円 | |
| 65歳以上の方 | ~330万円未満 | 収入額-110万円 |
| 330万円以上~410万円未満 | 収入額×0.75-27万5千円 | |
| 410万円以上~770万円未満 | 収入額×0.85-68万5千円 | |
| 770万円以上~1千万円未満 | 収入額×0.95-145万5千円 | |
| 1千万円以上 | 収入額-195万5千円 |
| 年金受給者 | 公的年金の収入額 | 所得計算式 |
|---|---|---|
| 65歳未満の方 | ~130万円未満 | 収入額-50万円 |
| 130万円以上~410万円未満 | 収入額×0.75-17万5千円 | |
| 410万円以上~770万円未満 | 収入額×0.85-58万5千円 | |
| 770万円以上~1千万円未満 | 収入額×0.95-135万5千円 | |
| 1千万円以上 | 収入額-185万5千円 | |
| 65歳以上の方 | ~330万円未満 | 収入額-100万円 |
| 330万円以上~410万円未満 | 収入額×0.75-17万5千円 | |
| 410万円以上~770万円未満 | 収入額×0.85-58万5千円 | |
| 770万円以上~1千万円未満 | 収入額×0.95-135万5千円 | |
| 1千万円以上 | 収入額-185万5千円 |
| 年金受給者 | 公的年金の収入額 | 所得計算式 |
|---|---|---|
| 65歳未満の方 | ~130万円未満 | 収入額-40万円 |
| 130万円以上~410万円未満 | 収入額×0.75-7万5千円 | |
| 410万円以上~770万円未満 | 収入額×0.85-48万5千円 | |
| 770万円以上~1千万円未満 | 収入額×0.95-125万5千円 | |
| 1千万円以上 | 収入額-175万5千円 | |
| 65歳以上の方 | ~330万円未満 | 収入額-90万円 |
| 330万円以上~410万円未満 | 収入額×0.75-7万5千円 | |
| 410万円以上~770万円未満 | 収入額×0.85-48万5千円 | |
| 770万円以上~1千万円未満 | 収入額×0.95-125万5千円 | |
| 1千万円以上 | 収入額-175万5千円 |
注釈:専従者控除
白色専従者控除額
- 配偶者である事業専従者…86万円
- 配偶者以外の事業専従者…50万円
ただし、専従者控除前の所得金額の1/2が上記金額に満たないときは、専従者控除前の所得金額÷(事業専従者数+1)=事業専従者控除額
所得控除等の種類
1 雑損控除
災害・盗難・横領により住宅や家財などに損害を受けた場合の控除で、次のいずれか多い方の金額が控除額になります。
- 差引損失額(損害金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等×10%)
- 差引損失額のうち、災害関連支出の金額-5万円
2 医療費控除
(A)か(B)のいずれかを選択します。
(A)通常の医療費控除
医療費-補てんされる保険金等-10万円または「総所得金額等の5%」のいずれか少ない額=控除額【最高200万円】
(B)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
特定一般用医薬品等購入費-補てんされる保険金等-12,000円=控除額【最高88,000円】
添付書類
医療費控除の明細書(昨年1月から12月までの1年間に支払った医療費の領収書を元に集計し、作成していただきます。領収書を提出する必要はありません。)
セルフメディケーションの場合は、明細書に加え一定の取組みを証明する領収書(原本)や結果通知表(写し:勤務先や保険者のわかるものが必要)など。
おむつ代について医療費控除を受ける場合は、医療機関発行の「おむつ使用証明書」、2年目以降は市(介護保険係)が発行する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」でも可能です。
3 社会保険料控除
支払った保険料や給与から引かれている社会保険料の合計額が控除額になります。
(健康保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、労働保険料、国民年金保険料、国民年金基金掛金、厚生年金保険料、各種共済組合掛金、農業者年金保険料など)
生計を一にする扶養親族が受け取る年金から天引きされている国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料は、扶養している方の控除の対象にはなりません。
添付書類
国民年金の場合は「社会保険料控除証明書」、各種保険料の領収書など
4 小規模企業共済等掛金控除
3種類の支払合計額=控除額
- 小規模企業共済法の共済契約(旧第二種共済契約を除く)に基づく掛金
- 確定拠出年金法の企業型・個人型年金加入者掛金
- 心身障害者扶養共済制度の掛金
添付書類
掛金の領収書
5 生命保険料控除
生命保険料は、一般生命保険料(新・旧)、個人年金保険料(新・旧)、介護医療保険料(新)の5種類あります(平成23年以前契約分が旧契約、平成24年以後契約分が新契約)。下表のとおり、新・旧の区分により計算式と控除額が異なります。生命保険・介護医療・個人年金ごとに控除額を計算し、合計します。
- 生命保険分の控除額
新生命保険(最高2.8万円)+旧生命保険(最高3.5万円)=控除額(最高2.8万円:旧生命保険が2.8万円超の場合は最高3.5万円) - 介護医療分の控除額(最高2.8万円)
- 個人年金分の控除額
新個人年金(最高2.8万円)+旧個人年金(最高3.5万円)=控除額(最高2.8万円:旧個人年金が2.8万円超の場合は最高3.5万円)
1.+2.+3.=控除額合計【最高70,000円】
| 支払保険料の金額 | 控除額 |
|---|---|
| ~12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 12,000円超~32,000円以下 | 支払保険料×1/2+6,000円 |
| 32,000円超~56,000円以下 | 支払保険料×1/4+14,000円 |
| 56,000円超~ | 28,000円 |
| 支払保険料の金額 | 控除額 |
|---|---|
| ~15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 15,000円超~40,000円以下 | 支払保険料×1/2+7,500円 |
| 40,000円超~70,000円以下 | 支払保険料×1/4+17,500円 |
| 70,000円超~ | 35,000円 |
6 地震保険料控除
(1)旧長期損害保険料
平成20年度から損害保険料控除は廃止されました。
平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等に係るもので、保険期間が10年以上あり、満期返戻金が支払われるものが旧長期損害保険料として控除対象となります。
支払保険料
- (ア)5,000円以下の場合…支払った保険料の全額
- (イ)5,000円を超え15,000円以下の場合…支払保険料×1/2+2,500円
- (ウ)15,000円を超える場合…一律10,000円
(2)地震保険料
支払った保険料のすべてが地震保険契約等に係るもののみ該当
支払保険料
- (ア)50,000円以下の場合…支払保険料×1/2
- (イ)50,000円を超える場合…一律25,000円
(3)旧長期損害保険料と地震保険料の両方ある場合
- (ア)(1)および(2)により計算した金額の合計額が25,000円以下の場合…当該合計額
- (イ)(1)および(2)により計算した金額の合計額が25,000円を超える場合…一律25,000円
一つの保険契約で、地震保険料と旧長期損害保険料の両方に該当する場合は、1契約ごとにどちらか有利な控除を選択します。
7 障害者控除
- 一般の障害者(本人・控除対象配偶者・扶養親族)1人につき…26万円
- 特別障害者…30万円
特別障害者…身体障害者手帳の1級または2級の方、精神障害者保健福祉手帳の1級の方、療育手帳のA判定の方、介護保険の障害者控除対象者認定書で特別障害者として認定された方、心神喪失の状況にある方など - 同居特別障害者…53万円
特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、自己や配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方
8 ひとり親控除
婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件に全てに当てはまる方…30万円
- 事実上、婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
- 生計を一にする子(総所得金額等が48万以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない)がいること。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
9 寡婦控除
次の2つの要件のいずれかに当てはまる方…26万円
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が500万円以下の方
- 夫と死別した後婚姻していない人又は夫の生死が明かでない一定の方で、合計所得金額が500万円以下の方
10 勤労学生控除
- 本人が勤労学生である場合…26万円
(大学・高校・盲学校などの学生・生徒で、合計所得金額が75万円以下で、このうち自己の勤労によらない所得が10万円以下である方)【在学証明書添付】
11 配偶者控除
- 下表参照
- 前年の合計所得金額が48万円以下である場合
- 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円以下である場合
- 内縁関係や事業専従者は該当しません
| 配偶者控除額 | 区分 | 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 | ||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
| 一般の控除対象配偶者 (70歳未満) |
33万円 | 22万円 | 11万円 | |
| 老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
38万円 | 26万円 | 13万円 | |
12 配偶者特別控除
- 下表参照
- 内縁関係や事業専従者は該当しません。
- 控除を受けようとする方の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除は受けられません。また、夫婦がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。
| 配偶者の 合計所得金額 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 | |||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
| 配偶者特別控除 | 48万円超 95万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 95万円超 100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | |
| 100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
| 105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
| 110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
| 115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
| 120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
| 125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |
13 扶養控除
- 一般扶養親族(16歳~18歳、23歳~69歳)1人につき…33万円
- 特定扶養親族(19歳~22歳)1人につき…45万円
- 老人扶養親族(70歳以上)1人につき…38万円
- 同居老親等(70歳以上)1人につき…45万円
14 基礎控除
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超~2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超~2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
税額控除
寄附金税額控除
市・県民税で寄附金税額控除の対象となる寄附は以下のものです。
- (ア)地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金【ふるさと納税】や災害義援金
- (イ)兵庫県共同募金会に対する寄附金
- (ウ)日本赤十字社兵庫県支部に対する寄附金
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)の控除額の計算方法 (PDFファイル: 78.6KB)
ふるさと納税について
2,000円の自己負担により、任意の地方公共団体への寄附金(ふるさと納税額)から2,000円を引いた金額分の税額(所得税+市・県民税)が軽減される制度です。例えば、50,000円の寄附をした場合、48,000円分の所得税と市・県民税が減額されます。ただし、軽減額には上限があります(注釈)。
税額控除額は下記の1.、2.、3.の合計です。【所得税率10%の方が50,000円を寄附した場合】
- 所得税控除額(申告特例控除額)…(50,000円-2,000円)×10.21%=約4,901円
- 市県民税の基本控除額…(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
- 市県民税の特例控除額…(50,000円-2,000円)×(90%-10.21%)=約38,299円
1+2+3:控除額合計=4,901円+4,800円+38,299円=48,000円
(注釈)3の特例控除額は、市・県民税所得割額(調整控除後)の20%が限度です。
ふるさと納税ワンストップ特例について
ふるさと納税をされた方が、確定申告をしなくても所得税と市・県民税の軽減を受けることができる特例です。もともと確定申告が不要な給与所得者等が、寄附をする自治体に申請することにより、寄附先が5団体以下の場合には、確定申告書の提出なしで、所得税の軽減分も含めて市・県民税がまとめて減額されます。
注意点
6団体以上の自治体にふるさと納税をされた場合や確定申告をされた場合は、ワンストップ特例は無効となり、ワンストップ特例申請をした寄附もすべて含めて確定申告を行う必要があります。なお、ワンストップ特例を適用してもしなくても軽減額は同じになります。
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に一定の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
令和3年度個人市民税・県民税から、合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となりました。
1.課税所得金額が200万円以下の方
下記の1.と2.のいずれか少ない額の5%(市民税3%・県民税2%)相当額
- 人的控除額の差の合計額
- 個人住民税の課税所得金額
2.課税所得金額が200万円超の方
下記の1.から2.を差し引いた額の5%(市民税3%・県民税2%)相当額
- 所得税との人的控除額の差額の合計額
- 合計課税所得金額から200万円を差し引いた金額
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円となります。
| 人的控除 | 所得税の控除額 | 市県民税の控除額 | 人的控除額の差 |
| 障害者控除(一般) | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| 障害者控除(特別) | 40万円 | 30万円 | 10万円 |
| 障害者控除(同居特別) | 75万円 | 53万円 | 22万円 |
| 寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| ひとり親控除(母)※1 | 35万円 | 30万円 | 5万円 |
| ひとり親控除(父)※1 | 35万円 | 30万円 | 1万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| 扶養控除(一般) | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 扶養控除(特定) | 63万円 | 45万円 | 18万円 |
| 扶養控除(老人) | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
| 扶養控除(同居老親) | 58万円 | 45万円 | 13万円 |
| 基礎控除※2 | 48万円 | 43万円 | 5万円 |
(※1)ひとり親控除で、父の場合、旧寡夫の差が適用されるため、人的控除の差が母と父で異なります。
(※2)調整控除、寄附金控除に用いる基礎控除の人的控除の差は、合計所得により基礎控除が逓減・消失しても、一律5万円となります。
| 納税義務者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
| 900万円以下 | 5万円 | 10万円 |
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | 6万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 3万円 |
| 納税義務者の合計所得金額 | 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 |
配偶者の合計所得金額 50万円以上55万円未満 |
| 900万円以下 | 5万円 | 3万円 |
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | 2万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
住宅借入金等特別税額控除
税源移譲に伴い、平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、税源移譲により所得税が減額となり、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、申告により、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
住宅借入金特別税額控除については、平成21年度税制改正において、平成21年から平成25年までに入居した方について所得税から控除しきれなかった控除額を翌年度分の個人住民税から控除する新たな制度が創設されました。この制度は延長され、令和4年12月31日までに入居した方についても適用されます。なお、この制度の控除を受けるための手続きについては、給与支払報告書等に所要の改正を行い、申告を不要とする仕組みとすることとされました。
これに伴い、税源移譲に伴う平成18年末までに入居した方に対する住宅借入金等特別税額控除についても、平成22年度分以降は、上記と同様の仕組みのもとで申告を要しない制度となりました。
パートと税
| 給与収入金額 (パート収入金額:注釈) 〈下段は所得額に換算〉 |
妻に税金がかかるか 所得税 |
妻に税金がかかるか 市・県民税 |
配偶者控除の 所得税 |
配偶者特別控除の 所得税 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93万円以下 〈38万円以下〉 |
かからない | かからない | なる | ならない | ||
|
93万円超103万円以下 |
かからない | かかる | なる | ならない | ||
| 103万円超216万円未満 〈48万円超133万円未満〉 |
かかる | かかる | ならない | なる | ||
|
216万円以上 |
かかる | かかる | ならない | ならない | ||
(注1)控除を受けようとする納税義務者の合計所得金額が1千万円を超える場合は、妻の所得にかかわらず配偶者控除、配偶者特別控除は受けられません。
(注2)パート収入金額は、その年分の所得税、その年の翌年度の市・県民税の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5306









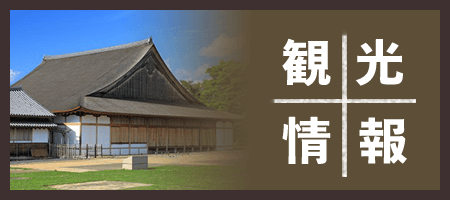
更新日:2023年12月22日